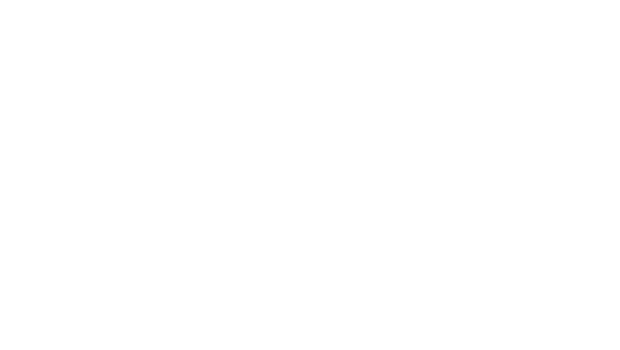
いつもの海苔と何が違う? 「青まぜ」ってどんな海苔?
東京湾に浮かぶ人工島「海ほたる」。海上パーキングエリアである海ほたるには、ドライブ中の休憩だけではなくその場で楽しめる施設がたくさんあります。展望デッキや幸せの鐘などはフォトスポットとしても人気。そんな中、おにぎり協会が気になるのはやはり地域の特産品を販売している「房の駅」です。千葉県の美味しいが詰まったお店は何度訪れても新しい発見があるよう。

そんな中で気になったのが海苔コーナーです。
香りが良く、味もおいしいと言われている千葉の海苔。これは、東京湾が海苔の生育に適していたためだそう。

そしてこちらも同じく海苔ですが「青まぜ」と書いています。青まぜとはなんなのか、気になりチェックしてみました!
「青まぜ」ってどんな海苔?
「青まぜ」、つまり「青混ぜ海苔」とは、黒ノリにアオノリ類を混ぜた海苔のこと。混ぜることによって、青ノリの豊かな香りと黒ノリの旨味のどちらも楽しめるというわけです。千葉県では木更津地域を中心に生産され高い品質で人気。
水産総合研究センター(東京湾漁業研究所)が千葉県の特産品である「青混ぜ海苔」に最も適したアオノリとして「キヌイトアオノリ」を選定し、母藻(種の元)の培養技術及び人工採苗技術を開発したことでも最近は注目され、2022年の漁期からこの技術を用いた青混ぜ海苔の生産も開始されています。(出典: 千葉県「水産総合研究センターによる青混ぜ海苔の安定生産技術開発及び『青混ぜ海苔フェア』での千葉海苔のPRについて」)
「大宝律令」において、年貢として納める海産物の一つとして指定されていた海苔。「海苔の日」は2月6日に制定されていますが、これは「大宝律令」が施行された西暦702年1月1日を新暦に換算すると2月6日だからだそう。今も昔も、海苔は日本人の食生活に欠かせない食品だとわかりますね。
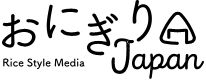





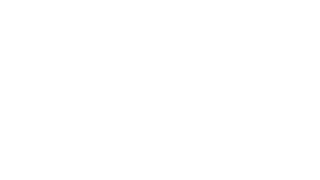
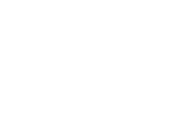

0件のコメント
コメントはまだありません。