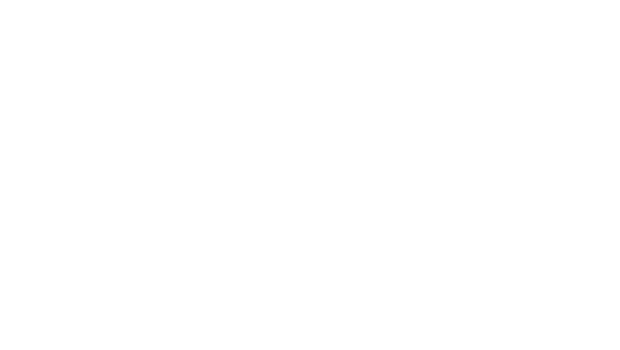
【おにぎりサミット】一次産業地に新たな価値を 魅力あるコンテンツが地域力を変えるのか
2025年2月7日(金)に開催した「おにぎりサミット2025」。様々な角度からおにぎりを考えるトークセッションが行われました。そのひとつが「一次生産地の新たな価値化『ワーケーション』や『ローカルフードツーリズム』で変える地域力」です。
「ワーケーション」という言葉が日本に登場したのは2015年ごろと言われています。「work(ワーク)」と「vacation(バケーション)」を組み合わせた言葉で、休暇を取りながら一部の時間を労働に充てる働き方が「ワーケーション」。そんなワーケーションに注目している自治体から現場の声を伺いました。
登壇したのは歌山県みなべ町 山本秀平町長、新潟県南魚沼市 林茂男市長、埼玉県深谷市 小島進市長、愛媛県今治市のi.i.imabari!推進課 永井秀樹課長、農林水産省大臣官房政策課 食料安全保障室 国民運動グループ長 小宮 恵理子さん、コンテンツツーリズム学会 増淵敏之会長、日本ウェルビーイング推進協議会代表理事 島田由香さん、タレントで今治・しまなみ自転車大使も務めている道端カレンさん。トークセッションの進行は今治エール大使 IMABALINA Ambassadorでタレントの木野山ゆうさんです。
一次産業をコンテンツに変える

通称「梅ワー」と呼ばれる「梅収穫ワーケーション」を実施しているのはみなべ町です。山本町長によると「みなべ町で働いている人の34%が一次産業で就業。さらにその中でも3割の方が梅を作っている」とのこと。梅ワーを始めたきっかけについては「みなべ町でも人口は減っているが、減るものは仕方ないですよね。その中で何ができるのかと考えてワーケーションの取り組みをはじめました」と話してくれました。

その梅ワーを企画・運営しているのが島田さんです。東京生まれの島田さんですが、今は住民票もみなべ町に移すほど。「梅ワーをはじめて4年になりますが、きっかけは農家さんが収穫の時に人手が足りなくて困ってると聞いたことです。人手が足りなくても梅は待ってくれません。そこで、ワーケーションとして和歌山にきてもらって、一日3、4時間でいいから農家を手伝おうよとはじめたの最初です。参加者は都心を中心としたサラリーマンの人が多く、2022年の1年目から123人きてくれました」。島田さんが意外だったのは、参加者だけでなく、受け入れ側の農家にとってもウェルビーイングの向上が見られたことだそう。実際にサミットに参加していた梅農家さんは「6月になり、収穫が始まるのがいやだったけど、今は6月が待ち遠しい。来てくれる人とのつながりを感じるようになった」と受け入れ側も満足度が上がっていると話してくれました。梅ワーは内閣府の優良事例にも認定され、ほかの地域の一次産業にも応用できると期待を集めています。

食べ物のおいしい魅力がコンテンツになると話してくれたのは南魚沼市の林市長です。「南魚沼市では田植えが終わったばかりの季節に『グルメマラソン』というのを実施しています。まだ遠くに雪が残っている風景を見ながらのマラソンで、楽しみながら走ってもらうことを目的にしています。給水所だけでなく、途中でおにぎりを食べるスポットもあるし、走り終わった後は南魚沼産コシヒカリの食べ放題が待っています」。ほかにも、自転車で町を走る『グルメライド』もあり、参加者は運動しているはずなのに太って帰る人もいるんだとか。
そして、南魚沼市といえば、昨年初めて開催したおにぎりサミットローカルの第一回開催地でもあります。「隣の町ではフジロックがありますが、うちでは『おにぎり&ミュージックフェス』を開催しました。音楽イベントはもちろんですが、敷地内で開催したおにぎりサミットローカルも常に行列で大いに盛り上がりました」。

農業をアピールするためにさまざまな施策を行っているのは深谷市です。深谷市の小島市長はふっかちゃんとステージに登場。「深谷市はねぎも有名ですが、ブロッコリーも日本一。私は花園ICにアウトレットを誘致しましたが、アウトレットはあくまでも集客のためで、農業をアピールしたいと思っています」と小島市長。

アウトレット内には『深谷テラス ヤサイな仲間たちファーム』というテーマパークがあり、これはキユーピー株式会社によるもの。「楽しみながら野菜や農業の魅力を知ってもらいたいんです。道の駅や直売所ではなく野菜を取りに畑にきてもらったり、楽しみながらおいしいものに触れてもらいたいと思っています」。

一次産業には自然環境保全の側面もありますが、この自然環境を最大限に生かしたいと考えているのが今治市です。永井課長は「今治市は、ちょうど合併20周年を迎えることができ、合併した12地域の魅力を改めて掘り起こしながらPRに力を入れています。今治市へ観光にお越しいただければ幸いだし、実際に移住したいと言ってもらえる街になってきていると感じています」と話しました。

2020年ごろからトライアスロンをきっかけで今治市と関わりができたというのは道場さんです。「すごくいい場所だなと、最初に訪れた時に思いました。海外からもサイクリストが参加して、しまなみ海道を走る自転車の大会もあるんですよ。私がいいなと思っているのはそれだけじゃなく、道の駅などで自転車を借りて、借りた場所とは違うところで乗り捨てできるようなレンタルの仕組みがあることです。誰もが気軽に自転車に乗り、自然の景色を楽しむことができるので、ぜひ多くの人に今治市に観光に来てもらいたいです」と道端さん。

道端さんの言葉に木野山さんも「温暖な気候で海あり、山あり、渓谷あり・・・今治は本当にすてきな場所なんです。大人になって市外に出てみると改めて感じる魅力が多いと感じています。より多くの方に今治市に興味・関心を持っていただけると嬉しいですね」と頷いていました。
日本の食は海外からも注目されるコンテンツ

自治体の話を聞いて「各市町村のみなさまは地域にあるものを最大限生かしているのが改めてわかる」と話すのは農林水産省の小宮さんです。「現在は生産の現場と消費者の現場が遠いので、食べているものがどういう状況で生産されているのかイメージがわからなくなっている状況があると思っています。それを知ってもらうための活動をしているので今日聞いたみなさまの話がとても心強く、まさに優良事例。一緒にPRしていきたいです」。
また、海外での認知の高さに注目しているのはコンテンツツーリズム学会の会長であり、法政大学大学院で教授を務める増淵さんです。

「日本のコンテンツの特徴は、多様性そのもの。アメリカの漫画を考えたら基本的にはマーベルコミックのようになるけど日本はそうではありません。野球漫画というジャンルを見るだけでもその中にもスポ根から恋愛を持ち込んだ作品まであり、ひとくくりにはできません。グルメ漫画もしかり。こういった多様性はどのコンテンツにも見られます。音楽をみると、K-POPは選択と集中で、力をつけ海外でも人気を得ました。一方の日本の音楽は演歌からヒップホップまで幅広く、浸透には時間がかかります。でもこの多様性がようやく芽を出してきたのではないでしょうか。日本の食も同じで、ようやく海外に認知されてきてまさに勝負の時期がきたかなと感じています」。
多様性のある日本らしいコンテンツは今後、日本各地を盛り上げるだけでなく海外からも注目されていくのでしょうか。未来への期待感の高まるトークセッションとなりました。
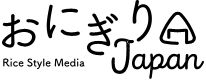





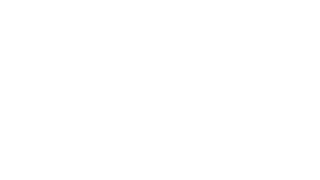
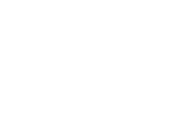

0件のコメント
コメントはまだありません。