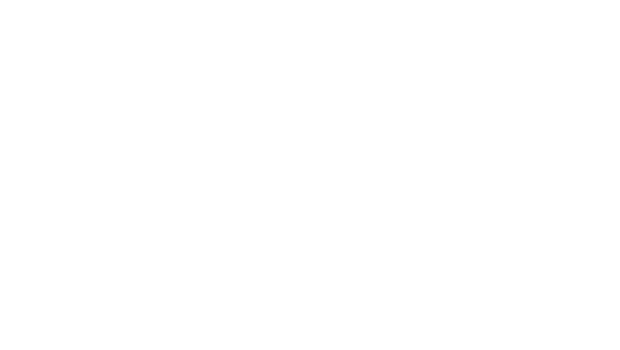
田植えの季節に考える、ごはんが食卓に届くまでの道のり
ゴールデンウイークを過ぎたころから、各地では田植えが行われます。おにぎりアンバサダー小池理雄さんによると、二毛作を行っている場所では、麦の刈り取りを待って5月終わりから6月ごろに田植えを行うことも多いそう。水を張った田んぼに苗が整然と植えられていく様子は、日本ならではの景色とも言えます。
さて、ここから田んぼではどうやって稲が育っていくのでしょうか。
お米づくりの1年サイクル
-
種もみ(3月下旬~4月)
お米の種となる「もみ」を水に浸して発芽を促し、病気を防ぐために温湯消毒や塩水選などを行います。 -
育苗(4月上旬~下旬)
発芽した種もみを苗箱にまいて、ビニールハウスなどで育て、田植えに適した苗に成長します。 -
田植え(5月上旬~6月)
育った苗を水を張った田んぼに植えます。手作業での作業でしたが、現在は田植機を使うのが一般的です。田植え後は水の管理、除草、病害虫防除、肥料の追加などを行います。これは天候との駆け引きが続く大事な工程になります。

収穫(9月~10月)
稲が黄金色に実り、穂が垂れてきたら収穫のタイミング。コンバインで稲刈りと脱穀を同時に行います。
-
乾燥(収穫直後)
収穫したもみを専用の乾燥機で乾燥させ、保存に適した水分量に調整します。 -
精米
乾燥・貯蔵された玄米は、必要に応じて精米され、白米として出荷されます。精米のタイミングは消費者や出荷先に応じて調整されます。
私たちの食卓にご飯が届けられるために、自然との付き合いと細やかな作業が積み重ねられているとわかります。「米」という漢字は「八十八」という漢字を分解して、稲作の工程の多さを表現しているという説も。この工程を知るとより大切にご飯を食べたくなりますね。
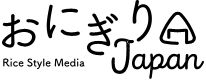





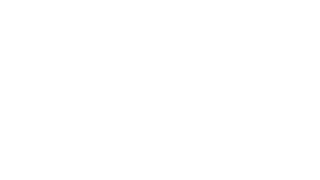
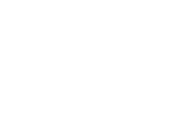

0件のコメント
コメントはまだありません。