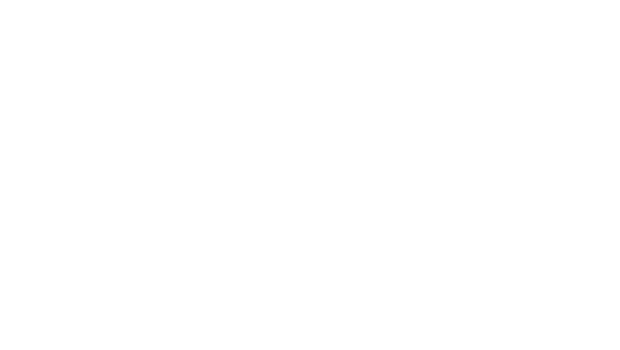
おにぎり協会クイズ【お米を知ろう!】Vol.89 「炊飯の歴史」
さて今回もごはんの歴史についてです。
「生米」をどのように加工して、どのように食べるのか…。実は私たちがスタンダートに理解している「炊く」という調理方法だけを、いままで日本人が行ってきたわけではありません。炊飯器からふっくらしたごはんをお茶碗に盛る…という絵柄だけが私たちの食文化ではないのです。ここに到るまで様々な変遷を経ているのですが…。
さてここで問題です。「ごはん」「炊飯」の歴史について正しく述べたものを次のア~エから選び、記号で答えて下さい。
ア.弥生時代から炊飯が広く一般的に行われていたことが、当時の土器から分かる。
イ.「炊く」という調理法が見られる前には「蒸す」ことが多く、そのごはんを「屯食(とんじき)」と呼んでいた。
ウ.現在のように米を生米の約2割増しにして、米が水を吸収してしまうまで炊く「炊き干し法」は江戸時代に定着した。
エ.お米を節約するために増量材として雑穀等を入れて炊飯したごはんを「強飯(こわいい)」と呼んだ。
おにぎり協会クイズ【お米を知ろう!Vol.89 解答】
正解はウの「現在のように米を生米の約2割増しにして、米が水を吸収してしまうまで炊く「炊き干し法」は江戸時代に定着した。」でした。
ア…羽釜が登場し始めた平安時代のころから「炊く」という調理法が見られるようになったと言います。それまでは主に煮たり蒸したりしていました。イ…蒸したごはんは「強飯(こわいい)」と呼んでいました。「屯食(とんじき)」とは今のおにぎりのルーツと言われるものです。エ…このようなごはんを「かて飯」と呼んでいました。
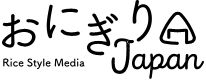






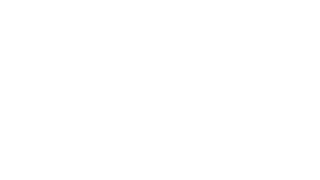
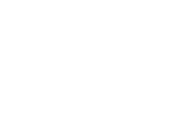

0件のコメント
コメントはまだありません。